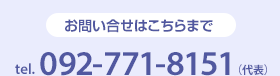がん治療センター
肺がん
肺がんについて
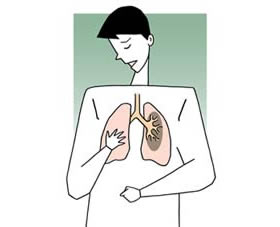
肺がんは現在でも増加傾向にあり、日本では1998年以後、がんの中で死亡原因の第1位です。
代表的な症状は、せき、呼吸困難、胸痛、血痰(けったん)などです。早期がんでは、無症状のことがほとんどで、健康診断時の胸部レントゲン写真や胸部CTなどで発見されることが多いのが現状です。
診断について
肺がんにはいくつかの組織型という種類があります。代表的なものとして以下の4種類があります。
| 腺癌 | 約50% |
|---|---|
| 扁平上皮癌 | 約30% |
| 小細胞癌 | 約10% |
| 大細胞癌 | 数% |
そのがんの性質により、小細胞癌とそれ以外では治療方針が異なってきます。胸部レントゲン写真や胸部CTで肺がんが疑われた場合は、診断のための検査を行います。喀痰細胞診や気管支鏡検査などを行いがんの診断と組織型を決定します。病変の部位によっては、皮膚から針を刺して細胞や組織片を採取することもあります。また、必要に応じて、遺伝子変異の検査も併せて行います。さらに頭部MRI、FDG-PET、骨シンチグラム検査といった肺がんが転移しやすい部位の検査を追加して、肺がんの進行度(臨床病期)を決定します。 肺がんそのものの大きさ、肺の近くのリンパ節への転移の有無そして他の臓器への転移の有無が臨床病期(I期からIV期)を決定します。
ただし、小さな早期がんなどの一部の肺がんは、外科的に切除しなければ、診断が困難なこともあります。
| I期 | がんが肺の局所に限局した時期 |
|---|---|
| II期 | |
| III期 | がんが局所から周囲の組織へ進展した時期 |
| IV期 | 他の臓器に転移をきたした時期 |
治療について
肺がん治療には外科治療(手術)・放射線治療・抗がん剤治療(化学療法・分子標的治療)・緩和支持療法があります。肺がんの組織型、臨床病期、遺伝子変異の有無、全身状態を考慮し、これらの中からもしくはこれらを組み合わせた治療方針を選択します。小細胞肺がんの場合は化学療法が治療の主体となり、手術や放射線治療が併用されることがあります。 非小細胞肺がんは局所で限局したI期、II期では手術が推奨されます。また術後の化学療法が組み合わされることがあります。 局所で進展したIII期の進行がんは放射線療法や抗がん剤治療、遠隔転移を認めるIV期では、化学療法が主体となります。一部のIII、IV期もしくは再発の肺がんでは、手術が行われる場合もあります。
| 小細胞肺癌の治療 | ||
|---|---|---|
| I期 | 手術+化学療法 | |
| II期 | 限局型 | 化学療法+放射線治療 |
| III期 | 限局型 | 化学療法+放射線治療 |
| III期 | 進展型 | 化学療法 |
| IV期 | 進展型 | 化学療法 |
| 再発 | 化学療法 | |
| 非小細胞肺癌の治療 | |
|---|---|
| I期 | 手術(+化学療法) |
| II期 | 手術+化学療法 |
| III期 | 手術±化学療法±放射線療法 分子標的治療 |
| IV期 | 化学療法・分子標的治療 |
| 再発 | 化学療法・分子標的治療 |
スタッフ
内科(呼吸器内科)、外科(呼吸器外科)、放射線科で連携して治療方針の決定をするとともに、集学的治療を行っています。 また緩和ケアチームとも連携し患者さんの生活の質(QOL)の向上を目指しています。