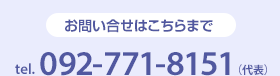検査部

- > 診療科・部門一覧
- > 検査部 - 生理機能検査
検査部 - 生理機能検査
ABI(足関節上腕血圧比)

足首と上腕の血圧を測定し、その比からABI値を算出します。通常、上腕と比べ足首の血圧はやや高値を示しますが、足の動脈に狭窄や閉塞が生じると足の血圧は低下します。動脈の狭窄や閉塞は下肢の動脈に発生しやすいため、ABI値を求めることにより、非侵襲的に下肢動脈の狭窄や閉塞の程度を推測します。
また、このABIを応用したもので、下肢血圧を大腿上部・下部、ふくらはぎ、足首の四カ所で測定し、病変の存在部位を推測する下肢分節血圧測定もあります。
PWV(脈波伝播速度)
心臓の拍動(脈波)が動脈を通じて抹消まで進むときの速度を計測します。上腕と足首の4カ所のセンサー間の距離と脈波の到達所要時間を計測し計算します。動脈が下腿ほど脈波が伝わる速度が速くなるので、PWV値が高いほど動脈硬化が進行していることを意味します。
※PWVとABIは、同時に測定出来ます。(所要時間:5~10分)
その他、測定値が血圧に依存しない測定法として、CAVI/ABIもあります。
CAVI(心臓足首血管指数)
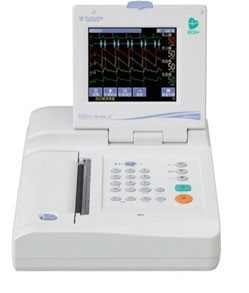
脈波速度を基に、血管の硬さを運動エネルギー消費量で表します。血圧に依存しない血管固有の硬さの指標となります。心臓と足首での脈波の時間差から脈波速度を割り出し、コンピューターが計算します。CAVI値が高いほど動脈硬化が進行していることを意味します。
TBI(足趾上腕血圧比)
足関節以下の血行障害を評価するのに重要な指標となります。特に糖尿病と透析の方は血管が石灰化しマンシェットによる圧縮が不十分になるためABI値が実際より高値にとなります。そのため末梢血管を足の親指を用いて計測するのがTBI値です。
SPP(皮膚灌流圧)

皮膚レベルの微小循環の指標で、どの程度の圧で微小循環が灌流しているかを示すものです。糖尿病性足病変などの石灰化症例の重症度評価や難治性潰瘍の治癒の予測、四肢切断レベルの判定などに有用です。(所要時間:30分~1時間)